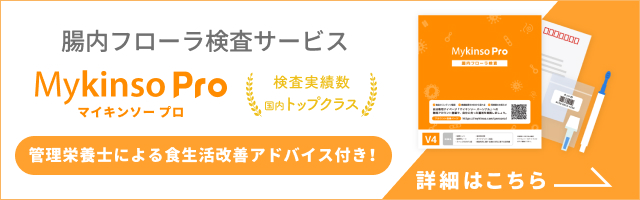以前のコラム(腸内細菌と病気・健康との関連ついて解説します 2024/11/28)で腸内細菌の話題に触れました。
今回は、腸内細菌の更に詳しいお話を出来たらと思います。
腸内細菌の種類はどのようにして決まる?
腸内細菌は良い菌、悪い菌などあるということが知られていますが、腸内に棲む細菌の種類はどのようにして決まるのでしょうか。
またその種類は変えることが出来るのでしょうか。

人間が生まれた時は、腸内には細菌が棲んでいないということが分かっています。
生まれてから色々な食べ物を摂取していくうちに、菌を獲得していき。3歳頃までにその人の腸内細菌叢が形成されてくることが分かっています。
母の腸内細菌の種類や分娩方法(帝王切開または自然分娩)、母乳栄養または人工乳、いつから固形食が開始されたか、抗生剤の使用歴があるかどうかなど様々な要因で常在する腸内細菌が決まってくるようです。
子どものビフィズス菌と母の持っているビフィズス菌が一致することが多いことが分かっていますが、これは母子の濃厚接触により菌が移行していると考えられています。

その後も、食生活や生活習慣などの影響で腸内細菌の割合は変動し、病的な変化も現れるようになります。双子であっても、腸内細菌を調べると全く一緒ではないということも分かっています。
腸内細菌は変動はするものの、基本となる種類は3歳を過ぎると変わらず、抗生剤の使用や病気などの影響で変動した後にも、元々持っていた種類に戻ってしまうようです。ですから、良い腸内細菌叢をキープするには、良い食事や生活習慣を継続する必要があるということになります。
食事による腸内細菌の変化について
食事の栄養素は簡単に分けると、「炭水化物」、「タンパク質」、「脂質」となります。この配分でも腸内細菌叢の変化が見られることが分かっています。
食事で高脂肪食を摂ると、体によくない代謝産物を生み出す悪い腸内細菌が増えることが分かっています。悪い腸内細菌というのは、腸管バリア機能に障害を与え、エンドトキシンという成分を血中に流入させることとなり、全身の炎症や脂肪細胞の増大に繋がることが分かっています。逆に低脂肪食や魚油含有食を摂っていると、良い腸内細菌が増え、腸管バリア機能を増強したり、体に良い短鎖脂肪酸を産生することが分かっています。
タンパク質の摂取についても、高タンパク質/低炭水化物の食事、いわゆる高タンパク食は体重減少のための食事療法として勧められてはいますが、注意が必要な点もあります。
日本人の食生活は、食の欧米化により、ここ半世紀で大きく変わってきています。肉類、卵、乳製品など動物性タンパク質の摂取が多くなり、植物性タンパク質の摂取量が減少傾向となっています。
動物性タンパク質の高い摂取はがん死亡率や全死因死亡率などと関連することが報告されています(Levine ME,et al. Low protein intake is associated with a major reduction in IGF-1, cancer, and overall mortality in the 65 and younger but not older population. Cell Metab. 2014 Mar 4;19(3):407-17.)。
ただし、摂取するタンパク質が植物由来である場合は、タンパク質摂取量が全死亡率やがん死亡率のリスクに関連することはないとのことです。
摂取するタンパク質源の違いにより、腸内細菌叢の変化を認めることも分かっており、腸内細菌の代謝産物が健康リスクに影響を与えていることが考えられます。
植物性タンパク質が多く含まれる食材は大豆が有名ですが、アスパラガスやブロッコリー、トウモロコシ、バナナなども植物性タンパク質が豊富です。是非食事に取り入れてみて下さい。

調味料も腸内細菌に影響することが分かっています。
”砂糖”は多く摂りすぎると、良い働きをする特定の腸内細菌の定着を妨げてしまうと言われています。
”塩分”も、乳酸菌に結合して、腸内細菌の乱れを助長し、炎症反応を亢進させることが分かっています。
減塩は血圧低下だけではなく、腸内細菌に対しても良い影響を及ぼすようです。

肥満と腸内細菌の関連について
肥満というのは、エネルギー(カロリー)の収支の均衡の破綻であり、摂取エネルギーが消費エネルギーを上回り、体内に脂肪が過剰に蓄積した状態です。

「症候性肥満」といって、甲状腺や視床下部から出るホルモンの異常などで病的に肥満となる場合と、摂食行動や運動不足、エネルギー代謝因子などが関連する「単純性肥満」があります。
腸内細菌叢はエネルギー代謝システムに大きな影響を与えている環境因子と言われており、肥満やメタボリックシンドロームの病態形成に深く関与していることが分かっています。
肥満型の腸内細菌叢を調べると、Firmicutes門/Bacteroides門比が高いことが分かっており、またBMI30を越える群では、Bacteroides門の細菌が大幅に少なくなり、Actinobacteria門の細菌が増加することが分かっています。
同一給餌条件下で飼育した無菌マウスと腸内細菌を保有するマウスで、無菌マウスは摂取量を増やしたのにも関わらず、体脂肪の蓄積量が低いという実験データ(Bäckhed F, et al. The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat storage. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004 Nov 2;101(44):15718-23)もあり、肥満に関して、食事摂取量のみではなく、腸内細菌の影響も大きいということが分かります。腸内細菌は食事を分解するとエネルギーを生成するので、それが過剰となってしまうと、肝臓や皮下に脂肪が蓄えられ、肥満となってしまうのでしょう。
これを摂れば間違いないという食事はない
健康のために腸内細菌や食事の情報を知ろうと思っている方であれば、でこの腸内細菌を増やせば健康になれる、この食事を摂っていれば大丈夫というものを知りたいと思います。しかし、この腸内細菌を増やせばいいといったことや、この食事を摂れば良いといった具体的なことは現時点では分かっていません。
お腹の中の腸内細菌は、腸内細菌叢といって、群れを作って暮らしています。割合は個人によって少しづつ異なり、その割合によって上手く代謝産物を産生出来たり、過剰に脂肪を蓄積してしまったり、余計な病的な物質を産生してしまったりするようです。
自分自身の腸内細菌叢を知るということで、今後の食生活や生活習慣を考える第一歩になると思っています。
土屋クリニックでは、Mykinso Proという腸内細菌を調べる検査を行っております。
少し費用はかかりますが、今後の食事や健康を考える上で一度自分の腸内細菌叢を知り、それを活かして頂ければと思っております。
まとめ
・腸内細菌は3歳までに概ね常在菌が決まるが、その後の環境や病気、生活習慣などで変動していきます。
・高タンパク食も、動物性タンパクの取り過ぎには注意しましょう。植物性のタンパク質の意識して摂取することを勧めます。
・自身の腸内細菌の種類や割合を知ることで今後の食生活の改善に活かすことが出来ます。興味がある方は一度腸内細菌検査を行なってみることをお勧めします。

■クリニック名
医療法人社団杏音会 土屋クリニック
■標榜科
内科、消化器内科
■院長
土屋 杏平
■コラム著者、監修
■所在地
〒116-0003 東京都荒川区南千住7丁目12−15
■電話番号
03-3806-9029