今回は「質の良い睡眠」をとるための方法について解説したいと思います。

質の良い睡眠とは?
「睡眠の質」については科学的に十分には定義されておらず、主観的な特徴により説明されることが多いです。
睡眠の質の指標としては、「入眠のしやすさ(入眠困難)」「途中で起きないか(中途覚醒)」「起床時の満足感(睡眠休息感)」などが挙げられます。
睡眠休息感の低下は、心理的ストレスや不安症状などと関連し、日中のイライラや疲労感などを悪化させるといわれています。

他にも、総死亡率や高血圧、糖尿病、心疾患などの危険因子となりうることが示唆されています。
睡眠というのは単に活動を休止して回復を待つという受動的な行動というよりも、環境への適応を高めるために積極的に心と身体を養う休養の場と考えた方がよいかもしれません。
睡眠時間との関係は?
よく「睡眠時間が足りない分、睡眠の質を高めよう」という風に言われることがありますが、睡眠の”質”と”時間”の関係は、前者が後者を補完できるような関係ではなく、お互いに影響し合っていると思って頂く方が良いと思います。
6時間未満の睡眠時間は睡眠休息感の低下と関連することが知られています。まずは睡眠時間の十分な確保が睡眠休養感の向上に必要です。

一方で、睡眠時間を十分確保しようとして、過剰にベッド上の時間を確保してしまうのは悪影響と言われています。必要睡眠時間以上に過剰臥床しないように注意しましょう。
睡眠は年齢とも関係があります。年齢が進むと深い眠りの割合が減少し、この影響で起きたときの熟眠感は減少します。いわゆる「睡眠が浅く感じられる」ようになってしまいます。
また年齢とともに、入眠するまでの時間も長くなり、朝方に目が覚めやすくなり、全体の睡眠時間も短くなります。
睡眠が浅く感じたり、睡眠時間が短くなったとしても、日中に眠気が生じたり、疲れを感じたりしなければ、生理的現象と考えて、あまり悩まくてもいいかもしれません。
睡眠の質を低下させる病気とは?
睡眠の質を低下させる原因が病気によるものの可能性があります。代表的なものとしては、「睡眠時無呼吸症候群」です。
いびきや無呼吸で血中酸素濃度が低下し、脳や心臓に負担をかけることで睡眠の質を低下させてしまいます。
ポリソムノグラフィーという検査で睡眠時無呼吸の重症度判定ができますので、気になる方は一度検査を行ってみて下さい。
重症に該当する場合はCPAP治療を行うことで症状改善に繋がる場合もありますので、一度ご相談下さい。(睡眠ポリソムノグラフィーやCPAPについて詳しく知りたい方は、こちらから)
他にも、レストレスレッグ症候群(むずむず脚症候群)やレム睡眠行動障害、アトピー性皮膚炎、更年期障害、前立腺肥大症や過活動膀胱などの頻尿など睡眠の質を低下させる病気として挙げられます。
睡眠の質を低下させる環境とは?
人間には「概日時計」という体内時計があり、起床後から日中にかけて太陽光に準じた十分な高照度光を浴びると、概日時計が調整され、睡眠と覚醒のリズムが整うようにできています。
朝日の光刺激によりメラトニンという眠くなるホルモンの分泌が抑制され、14-16時間後くらいにメラトニンが分泌されるようになり、夜眠気が生じるようになります。
日中に日をきちんと浴びなかったり、夕方以降に高照度光にさらされ続けると、睡眠と覚醒のリズムが整わなくなってきてしまい、睡眠の質が低下してしまいます。
朝起きたら日を浴びて、夕方以降は光暴露を控えて、寝室はできる限り暗所にすることが睡眠の質を高めることができます。

夜にテレビやパソコン、スマートフォンを長時間見続けるのは目や脳に光暴露を与えますので、気をつけましょう。
ベッドルームも朝日がカーテンから薄く漏れてしまうと、その光で早朝に起きてしまい、睡眠時間が確保できなくなる恐れがあります。
寝室は光が入らないように、遮光カーテンや窓に遮光シートを貼るなど工夫すると良いでしょう。
寝室の温度も重要です。人間の身体は深部体温が下がることで入眠が促進されるように出来ているので、就寝直前の運動や入浴はあまり良くないのと、室温は暑すぎない方がよいです。
就寝中の騒音も睡眠の質を低下させるので、就寝中に音楽を流すのもあまり推奨はされません。住宅での騒音の影響が大きい場合は、防音措置を考えましょう。
睡眠の質を良くする生活習慣は?
身体活動量が低く、運動習慣がない場合は、睡眠の質が下がることが知られています。
睡眠の質を良くしたい場合は、日常生活に運動を取り入れましょう。
運動の種類としては、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動がおすすめです。

食事についても、朝ご飯を食べないことは、覚醒を遅らせて、睡眠・覚醒のリズムが整いづらくなります。軽食でもよいので食べることで睡眠の良いリズムを作ることが出来ます。
また就寝前の食事摂取や飲酒は中途覚醒といって、途中で起きてしまうことを促進させます。アルコールは鎮静作用によって、入眠を促しますが、体内でアセトアルデヒドに代謝されることで覚醒作用が強くなるので、最終的には睡眠の質を下げてしまうのです。
カフェインも夕方以降の摂取は控えることが大事です。午前中の摂取であっても、摂取量が多い(1日カフェイン400mg以上、コーヒー700ml程度)と夜間の睡眠に影響を及ぼすと言われています。
タバコも紙巻き・電子問わず、ニコチンが覚醒作用を有するので、就寝前の喫煙は避けましょう。
まとめ
・睡眠の質を上げるにはある程度の睡眠時間確保(6時間以上)が大事です。
・睡眠の質に影響する病気もあるので、いびきや無呼吸など指摘される場合は、検査や治療が必要です。
・睡眠の質を上げるためには、一度環境や生活習慣の見直しをしてみましょう。
最後に、睡眠の質でお悩みの方は是非一度医療機関でご相談下さい。
環境や生活習慣を変えても良くならない場合は、一度睡眠薬を使用し、良いリズムで眠れる習慣を作ることで、睡眠休息感を得られていくこともあります。
不眠や睡眠の質でお悩みの方は土屋クリニックまでご相談下さい。
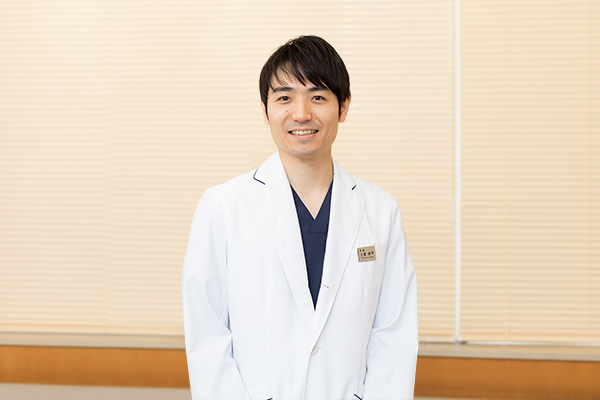
■クリニック名
医療法人社団杏音会 土屋クリニック
■標榜科
内科、消化器内科
■院長
土屋 杏平
■コラム著者、監修
■所在地
〒116-0003 東京都荒川区南千住7丁目12−15
■電話番号
03-3806-9029



